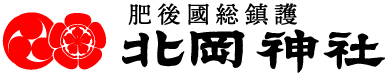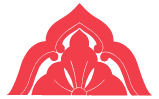
塩湯取神事

塩湯取神事の様子
塩湯取神事とは、例大祭にあたり神職及び総代一同が潔斎し心身を清めるのとともに、例大祭の神事での修祓(しゅばつ)に用いる塩水を汲み取る神事であります。
修祓とは、神事を斎行するにあたり清浄を保つめにお供え物や玉串、奉仕する神職や参列者等をお清めしお祓いすることをいい、これは大麻(おおぬさ)や塩湯(えんとう)などを用いて概ね神事直前に行います。
このうち塩湯とは塩を湯や水に溶かして、もしくはそのまま器に入れたもので、これを榊の小枝の葉先につけて振り祓ってお清めに用いることがほとんどです。ところが当神社ではこの塩湯の塩水を汲取るという故実に従い、現在もなお特殊な方法で行っております。
今から一千年以上もの昔の承平四年(934)、御祭神が京都の八坂神社より勧請される際、海路を経て白川を遡り小島村付近に上陸され、そこから府中に向かわれ御鎮座されたとあります。この謂れある小島村で例大祭に関する塩湯取の神事が行われるようになりました。
その内容は弘治三年(1557)の『三十三度御祭礼式』に記されております。旧暦六月七日に行われる神幸行列に先立ち、あらかじめ「掬垢離」(きくごうり)を行っていたと記されております。この「掬垢離」とは、小島村南婆浦の引潮時にできる川の中州を斎場として注連縄を張る「注連神事」に始まり、潮水に浸って穢を祓い身を清める禊祓いの行事でもありました。このことから「塩干河神事」とも呼ばれ、国司や勅使など地位の高い者もこれを行っておりました。
また、江戸時代末期の飽田・詫摩郡代(地方官)の日記にも記されております。それは郡代が社寺に関わる役目の中で、最も重要な勤めであったのがこの祇園社での掬垢離でありました。慶応元年(1865)元年旧暦六月朔日の条に、来る七日の「御代垢離(みよごうり)」に備えて郡代自身が潔斎の生活に入っていたことが詳しく記述されています。御代垢離とは、天皇の代わりに勅使として行う掬垢離であったので、このように尊称して記されていたものだと思われます。
潔斎期間を経て、祇園祭の前日にあたる七日の朝九時頃に屋敷を駕籠に乗って出発し、熊本城二の丸から祇園社の旧社地である二本木を通り、坪井川沿いを下り小島村の南婆浦へ向かう。ここで禊を行い身を清めた後に惣庄屋たちからのおもてなしを受けていました。その後、白装束に着替え駕籠に乗り祇園社近くの白川までもどり、その河原でも行水を行い再び身を清めて、そこから祇園社に向かい裃姿で参拝しその役目を終えていました。このような内容からしても、掬垢離が如何に厳粛に行われていた重儀であったのかを覗い知ることが出来ます。

塩湯取神事に向かう関係者一行
(昭和九年七月)
明治に入っても掬垢離は「塩湯取神事」として続けられ、神職と氏子総代関係者は羽織袴姿の出で立ちで人力車に乗り小島村まで出向いていました。「塩湯取」からもわかるとおり塩湯用の潮水を汲む神事であり、先ず参列者が潮に浸かり禊を行ってからお祓いをし、竹筒にその潮水を汲み取り、神社へ持ち帰り大祭の祭事に用いていました。
現在の「塩湯取神事」は、七月二十九日の朝に神職や氏子総代等関係者が車に乗って小島上町に向かいます。御祭神が京都から小島に上陸された際に、休息されたと言い伝えられている村上家を訪れます。その家は代々この神事に携わってこられたとされる元庄屋で、そこで神事に使う御幣と大麻を作ります。
それから、斎場とされる小島橋下流に向かい神事を執り行います。神事では、実際に潮水に浸かることは行いませんが、神職と総代のお祓いと御神酒を川に流し献酒をして清め参拝の後、再び村上家へ戻り着替えをして接待を受けます。
現在では、この日の早朝に河口から舟を出し沖の潮を汲んでもらったものを、総代が青竹で作った真新しい二本の竹筒に入れ持ち帰っています。
この後、御遷座で通られたといわれる道筋を辿り城山半田町まで進み、そこに鎮まる鳥子阿蘇神社の拝殿にて参拝の後に、ここも京からの一行を迎え接待したという家柄の宮本家から昔ながらの接待を受けます。

塩湯取神事に向かう関係者一行
(昭和九年七月)
ここでは伝承に則り自家製味噌で漬けた漬物と、黒砂糖を溶かし小麦粉を捏ねた「延べだご」で、年に一度しかない恒例のお茶請けで心尽くしのおもてなしがなされます。この後、神社に帰り塩水と延べだごをお供えし、直会が執り行われます。
「塩湯取神事」は、時代の変遷と共に交通事情の変化や河川改修等の事情により、神事の内容の変更も余儀なくされたところもありますが、現在もなお途絶えることなく続けられている特殊神事の一つでもあります。